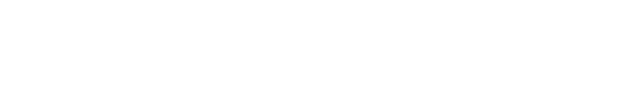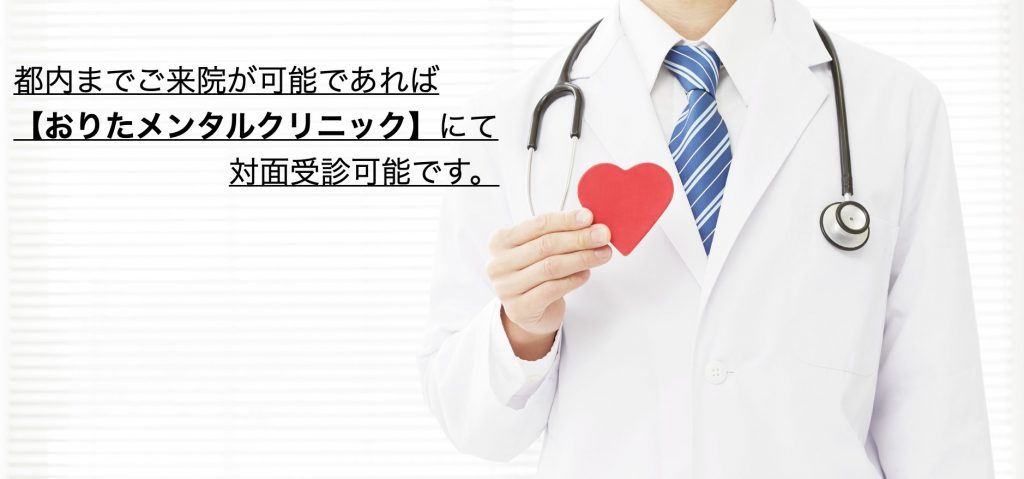【医師が解説】休職について【心療内科・精神科】
ここでは、休職について説明します。
目次
休職を考えたら
休職中について
復職について
コラム:休職中の心身の整え方
休職について
人間関係の悩み・過重労働など、"精神的なストレス"からうつ状態になることを"適応障害"といいます。
更に状態が悪化すると、"うつ病"へと進行します。
そんな時は早めに仕事やストレスの原因から離れて、心と身体を休めることが一番大事になってきます。
そのためには医師の作成した診断書を提出し、自分自身の状態や休養が必要な旨を職場に証明する必要があります。
多くの方は身体や心に症状が出るまで我慢し受診されます。
仕事を休むことや理不尽な人間関係から離れることは、逃げることではありません。
また自分の心と身体の健康を守るのは、自分自身しかいません。
疲れた心と身体に休息を与え、健康を取り戻すための手段の一つが、休職になります。
休職相談は当院まで気軽にご相談下さい。
休職とは「会社との雇用契約を継続したまま休むこと」
休職とは、会社との雇用契約を継続したまま休むことです。
退職の場合は雇用契約が終了していますが、休職の場合は籍が会社に残った状態であるため、復職が可能になります。
休職の条件は会社によって変わります。
会社によって、休職給の規定を設ける会社もあれば、怪我や病気以外の理由で休職を認める会社もあります。
休職を検討する方は、会社の人事部に相談するか、就業規則を確認するといいでしょう。
休職を考えた時に
まずは医師による診察が必要です。
診察の結果休職が必要と判断されれば、診断書が発行されます。
診断書の内容としては、病名や症状、休職の期間などが記載されます。
会社によって診断書に記載が必要な内容・文言がある場合や、一度に休職を指示できる期間に制限がある場合もありますので、診察の際にお伝えください。
前もって休職に必要な書類などについて確認しておくとスムーズです。
会社の就業規則・雇用契約書をもとに、以下の点をご確認ください。
・休職可能な期間はどのくらいか
・休職中の会社の規定
・会社ではどんなフォローが受けられるのか
(お試し出勤や午前のみの出勤など時短勤務の対応が可能か、など)
その後、医師が作成した診断書を職場に提出し休職に入ります。
診断書は多くの場合上司に提出しますが、会社によっては人事部や総務など提出先が異なることもあります。
また、どうしても職場に行けない場合には、電話で休職の指示を受けた旨を伝え、診断書は郵送で送る方もいらっしゃいます。
いずれかの方法で診断書を職場に提出して頂き、その後出勤はせずに自宅で療養することとなります。
もし診断書を出しても記載の内容のとおりに進まない場合には、速やかに再度受診するなどして主治医とその後の対応をご相談ください。
休職の期間はどれくらい??
一般的には2ヶ月から3ヶ月程度の期間になります。
ただし患者さんの状態や会社の就業規則・勤務年数などによって、休職できる期間も変わってきますので、患者さんと相談しながら決めていくことになります。
まず2ヶ月程度の期間で診断書を作成し、その後必要に応じて延長するケースが多いかと思います。
休職のメリット
傷病手当金が受給できる
傷病手当金とは、怪我や病気を理由に休職をした際に受給できる手当金のことです。
休職制度は会社によってさまざまですが、一般的には休職中に給料が支払われる会社は少ないです。
傷病手当金は、療養のために会社の給与が受給できなくなった方の生活を保証するものになります。
傷病手当金は以下の全ての条件を満たすことで受給可能です。
- 休職中に給与を受給していない
- 連続する3日間を含む4日間以上、勤務ができなかった
- 仕事に就けない(働けない)状態である
- 業務以外の理由で、怪我や病気の療養のため休職している
上記の条件を全て満たし、申請することで休職前の給与の3分2が受給できます。
支給期間は、支給開始から通算して最長1年6ヶ月です。
休職中、給与が受給できないデメリットを少なくできる手当金になります。
条件に合致する方は、必ず傷病手当金の申請をしましょう。
療養に専念できる
怪我や病気の方の場合、治療に専念できなければ、完治が遅くなります。
仕事に就きながら療養する場合、精神的にも肉体的にも負担が増えます。
また十分な治療時間が確保できない場合、怪我や病気が悪化し、長期入院が必要になる場合もあるのです。
一方で療養に専念できれば、完治が早くなり、復職がいち早くできるでしょう。
復職がいち早くできれば、自身にとっても会社にとってもプラスになります。
怪我や病気で苦しむ方は、休職して療養に専念し、早期の復職を目指しましょう。
ストレスが緩和できる
日々の業務や人間関係から生まれるストレスから開放されるため、メンタル面でいい影響が出るでしょう。時間的にも心理的にも余裕が生まれます。
休職中に今後のキャリアについて考えてみるのもいいでしょう。自身が今後どのようなキャリアを歩み、どうなりたいかを考えてみるのです。スキルアップを図りたい方は、休職中に資格の勉強をしたり、専門領域の知識を習得したりするといいでしょう。
また、休職中に家族との時間を共有することもおすすめです。
特に仕事が多忙で普段なかなか家族と時間が過ごせない方は、休職のタイミングで漢族との団らんを楽しむのもいいでしょう。
休職の流れ
休職するためには、まず医師の診断書が必要です。
心療内科・精神科を受診し、医師から診断書を作成してもらう
(当院では受診当日に発行し、ご自宅に郵送致します)
↓
上司もしくは人事総務部などに、診断書を提出する
(直接渡すのが難しい場合には、郵送でも可能)
↓
可能であれば即日、引き継ぎなどあれば最低限のみ行い、速やかに休職に入る
↓
休職中はしっかり自宅で療養しつつ、最低月一回程度診察を受ける
多くの場合、月ごとに傷病手当金の申請を行う
↓
主治医の許可が出れば復職に向けて、職場と調整を行う
(患者さんの希望によっては、退職や転職となる)
休職中の収入について
休職中は給与の代わりに、健康保険組合から"傷病手当金"が支払われます。
病気などで仕事ができない場合、生活を保障するため、給与の代わりに健康保険組合などから支給されるものです。
患者さんによって多少の差はありますが、給料の3分の2程度が最長1年半、保障される制度です。
受給するためには、傷病手当金申請書に医師による証明が必要となります。
病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(=待機期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
※傷病手当金以外にも、独自の給与保証がある会社もあります。
詳しくはコチラもご覧ください。
傷病手当金についての注意点
1. 最低限月に1回の診察が必要
申請する期間の状態や、医療関の受診日を健康保険組合に示す必要があります。
受診が一度も無い月は手当金が支給されません。
また、診察が無い以上申請書の記載も出来ません。
毎月の診察を忘れないよう、くれぐれもご注意ください。
また傷病手当金支給申請書の申請が通るかどうかは
各保険者の判断になりますのでご了承ください。
2. 記載日までの期間しか証明できない
傷病手当金は休職した期間を遡って請求するものになります
※前もって未来の期間を請求することは認められておりません
申請書の中には
”労務不能と認めた期間:令和○年○月○日〜令和○年○月○日”
と医師が記載する欄があります。
その期間に就労が出来なかった証明になりますので、その期間が過ぎてからでないと医師は記載・サインが出来ません。
1月1日〜1月31日の傷病手当金を申請する場合、医師がその証明を出来るのは1月31日以降になります。
1月20日の時点において1月分全ての記載を希望されても、証明および発行ができないので注意が必要です。
請求期間の締日が過ぎてからの郵送をお願い致します。
3. 初診日以降の証明しかできない
医療機関では初診日以降の分しか、申請書の記載ができません。
これは患者さんとお会いする前の期間については、医師として症状を証明することが出来ないからです
そのため傷病手当金申請を検討されている場合には、早めの受診をお勧めしております
当院への申請の仕方
各健康保険組合の書式がありますので、指定の書式を当院に郵送して頂ければ、医師記載欄を記載し返送いたします。
データやメールでのやり取りは、個人情報保護の観点からお受けしておりません。
申し訳ありませんが、紙ベースでの郵送でのやり取りを、お願い致します。
※最低月に1回の診察がなければ、支給されなくなりますので、ご注意下さい。
休職中の過ごし方について
休職に入ってしばらく、1週間〜2週間程度はゆっくり体を休めるようにしましょう。
その後体調と相談しながら、徐々に運動や趣味・外出などを行い、体力の回復に努めます。
徐々に体調が回復していくと少しずつ気力が出てきます。
それに伴い活動量も増え、外に出て何かをしてみようという日も増してきます。
気力が湧く日もあればそうでない日もありますが、焦らずに過ごしていきましょう。
仕事から完全に離れましょう。
まずは仕事から距離をとって、しっかり休んで頂くことが大事です。
体調を最優先に考えていただき、業務からしっかり離れること、最初は何もせずにぼーっと過ごすことが必要です。
そのため基本的には、休職中は業務への従事は禁止です。
業務連絡も基本的には禁止になります。
会社から離れても自らメールをチェックしたり、業務に関する連絡をしたりという生活だと、気持ちは全く休まらず、焦りばかり生まれて逆効果です。
完全に仕事から離れることが休職の目的ですので、休職に入っても頻繁に会社から連絡が来るなど、休まらないようであれば職場か主治医にご相談ください。
ただし、月に1-2回の職場への体調報告などを求められることはあります。
負担のない範囲で頻度や方法などは相談の上決定してください。
負担になるようなら、最初はご家族に代行してもらってもいいかもしれません。
少しずつ動くようにしましょう。
数日から1-2週間そのような時間を取り、少しずつ気分が上向いてきたら散歩をしたり、外出をしたり、外の空気に触れるようにしましょう。
その後は主治医と相談しながら、生活の目標を立てて過ごしていくことが望ましいです。
休職期間中は朝起きて職場に行く必要はありませんが、生活リズムを乱さないことが大切ですので、昼夜逆転しないように気をつけて下さい。
常識的な時間に就寝・起床して、日中にある程度活動できるように心がけていきましょう。
通院を継続しましょう。
休職中は2週間〜1ヶ月に1回、主治医の診察を受けるようにします。
症状の変化や経過、回復具合を確認しながら、必要に応じて休職期間を延長することもあります。
その後医師が仕事に戻っても問題ないと判断した場合は、復職の診断書をお書きします。
それを元に会社によっては産業医が復職の可否について判断し、問題なければ復帰となります。
過度な飲酒習慣には注意しましょう。
アルコールは体調不良や生活リズムの乱れだけでなく、うつ状態の悪化、アルコール依存症にも繋がりますので十分に注意しましょう。
家族の支援を受けましょう
効果的に療養生活を送り、早く職場に復帰するためにも家族の支援は不可欠です。
一人暮らしの場合でも、可能な限り家族のもとで療養することをお勧めいたします。
休職中に大切な「規則正しい生活リズム」
「動こうという気分になるのを待たずに、渋々でも起きてみたら案外やる気が出た」
「思ったより気分良く過ごすことができた」
「一度試してみたら、いい結果が得られたので、続けて行動してみようと思えた」
「行動してみたらいい気分になったので、もう一日やってみようと思った」
このようなサイクルを作り上げ気分を持ち上げていくことは、確立された心理療法の手法のひとつです。
コツは「行動してみることで、達成感を得る。そしていい気分になる」ということです。
まずは行動を活性化して、生活習慣を改善してみましょう。
成功体験の積み重ねが「案外やれる」「結構やれる」という自分への期待感や自信につながります。
小さな積み重ね、スモールステップを達成することを目指しましょう。
復職の仕方
しっかりと自宅療養を行い、心身ともに健康な状態に近いところまで回復したら、復職に向けて相談していきます。
元の部署に戻る方、あるいは配置転換や部署異動を行い環境を変えて戻る方など、復職の仕方は患者さんによって異なります。
症状の再発再燃を防ぐため、働きやすい環境で復職することが大事です。
職場としてどこまで対応できるか、患者さんの希望はどうか、そのあたりを相談しながら復職の時期・方法を決めていきます。
職場の対応が可能であれば、異動後の復帰や時短勤務での復帰を検討し、職場と摺り合わせていきます。
もちろん休職後に"転職"を選択し、新しい環境で仕事に復帰される方もいらっしゃいます。
復帰の仕方は人それぞれですので、休職中にご相談して決定していきましょう。
運動について
休職期間が長くなると
・昼夜逆転の生活
・生活リズムの乱れ
・睡眠不足
・孤独感、おっくう感
・運動不足
など、基礎体力の低下に繋がります。
体力とは
体力には「行動体力(=基礎体力)」と、「防衛体力」の2種類があります。
この2つは自転車の車輪のようなもので、2つで一つです。
いくら行動体力である筋力や持久力が高くても、暑さや寒さなどの外的環境に弱かったり、心配事を抱えたりして防衛体力が低くなっているとコンディションが崩れやすく、十分なパフォーマンスが発揮できない可能性が有ります。
そのため病気の予防、健康増進、生活の質の向上、日常の活動およびスポーツパフォーマンスを向上させるには、運動を通して行動体力と防衛体力に対して意図的に働きかける必要があります.
運動の重要性-病気との関連性
まず休職中は、無理をせずゆっくり休んで頂くことが第一前提ではありますが、症状として「疲労を感じやすい」「やる気が起こりにくい」というところから、体を動かすことが辛く感じるひとも少なくありません。
ですが体を動かさなすぎると、全般的に体力が低下し就労時にさまざまな弊害が生じます。
「運動によってうつ病・抑うつ症状が改善される」というデータが数多くあります。
うつ病になる原因として「セロトニンの分泌が少ない」と言われており、筋肉にあまり負担をかけない有酸素運動がセロトニンの分泌を促進させます。
そのため、運動をすることが推奨されています。
※セロトニンとは・・・
人間の精神面に大きな影響を与える神経伝達物質のこと。
セロトニンが不足すると精神のバランスが崩れ、うつ病を発症する原因と言われいる.
おすすめの運動:有酸素運動
筋肉を動かすエネルギー源として、糖質や脂質とともに酸素を使って行う運動のこと。
息が弾むくらいの強度で、比較的筋肉への負荷が軽い運動のことをいいます。
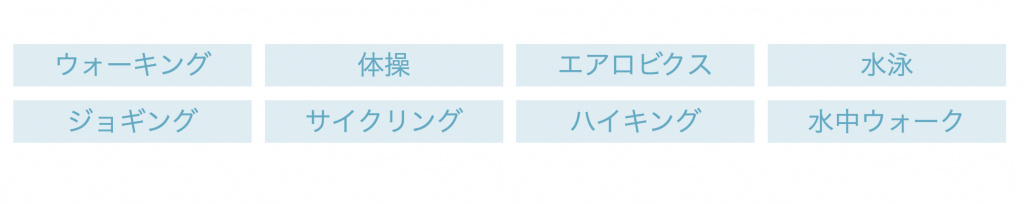
ちなみに・・・
脂質や糖質をエネルギー源として使うため、血中脂質や血糖の減少が期待でき、高血圧や高血糖・脂質代謝異常などの改善を促すことができます。
また、心肺機能の改善や骨粗鬆症の予防も期待できます。
睡眠について
休職している人以外でも、日本人の4〜5人に1人は睡眠になんらかの問題を抱えていると言われており、
・世界的にみても日本の睡眠時間は短いことで有名
・日本人の睡眠時間は年々減少傾向にある
ことはよく知られています。
睡眠-覚醒について
人の体には 約24時間の周期で変動するリズムがあり、睡眠覚醒リズムをコントロールしているものを概日リズム(体内時計)と言います。
脳の中の体内リズムによって睡眠や覚醒、体温、メラトニンなどのホルモンがコントロールされています。
メラトニンは概日リズム(体内時計)に働きかけることで、覚醒と睡眠を切り替え自然な睡眠を誘発する作用を持つため、睡眠ホルモンとも呼ばれています。
目覚めてから14〜16時間後に体内時計から指令が出て、メラトニンの分泌が高まることで深部体温が低下し急速に睡眠状態に導かれます。
朝の光は概日リズムをリセットする作用を持っており、朝日を浴びると脳にある体内時計が調整され、活動状態に切り替わります。
睡眠不足の影響
つぎに睡眠不足によって、どんな影響がでるのか具体的にみていきましょう。
脳機能への影響、身体の健康への影響、心の健康への影響、行動への影響などに分けてどんな影響があるか分けてみました。
「体に悪いから早く寝ましょう」「徹夜は止めましょう」などいろいろ言われますが、この内容を見るだけで確かに「睡眠不足」や「夜型の生活」は、健康や作業能率に負の影響を与えているのがわかります。
不眠症について
「寝つきが悪い」「夜中に目が覚めてしまう」「朝早く目が覚めてしまう」「熟睡感がない」など眠ることが難しいことが概ね1ヶ月以上続き、不眠が続くために日中の調子がすぐれない状態を指します。
原因
環境要因:暑さ、寒さ、明るさ、時差など
身体的要因:年齢、性差、痛み、痒みなど
心の要因:悩み、イライラ、精神的ストレスなど
生活習慣要因:飲酒、喫煙、カフェインの摂取、薬の副作用などが挙げられます
→不眠症は生活の質(QOL)の低下を招くばかりだけではなく、長期的にはうつ病のリスクを高めるなどの弊害もあり、早めの適切な処理が大切です。
治療
不眠の原因を探り取り除くとともに、睡眠への正しい知識を身につけて症状によって睡眠薬などを使用します。
睡眠のメカニズム
入眠前
①眠りにつくときには,深部体温をさげることで,脳と体をしっかり休息させる仕組みがあります。
深部体温を下げるために皮膚の表面から熱放散が働き、深部体温(体の内部の温度)が下がります。
②体温が下がったことに伴いそこから休息状態(体が軽い弛緩状態)になり、眠気が訪れます。(副交感神経優位)
入眠後
③睡眠中は「レム睡眠(浅い眠り)」「ノンレム睡眠(深い眠り)」のを90〜120分のサイクルで交互に繰り返しながら眠りが継続されます。
④睡眠中には成長ホルモン、メラトニン、コルチゾールなどのホルモンが分泌されており、健康維持・増進に関わる重要な役割を担い、睡眠と覚醒のリズムに大きく関わります。
※睡眠覚醒リズムをコントロールしているのは、人間の体に備わっている「体内時計(概日リズム)」です。
体内時計の周期は通常1日24時間より若干長いので、どこかでズレを調整しなければなりません。
その調整役を担っているのが太陽の光です。
朝に太陽の光を浴びることで目から光の情報が伝わり、体内時計がリセットされます。
睡眠のメカニズム-2
睡眠のリズムには2種類あります。それが「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」です。
この2つの睡眠を90〜120分のサイクルで交互に繰り返しています。
ノンレム睡眠は脳が休息している状態で、体も休んでいますが筋肉はある程度動いています。
ノンレム睡眠中は、心拍数や血圧などは安定し、深くゆったりとした呼吸になります。
眠りの深さは3段階あると言われていますが、深くなるほど脳は休息状態になります。
一方、レム睡眠の場合、全身の筋肉は弛緩していますが脳は活発に動いている状態です。
この間に記憶の整理や定着が行われています。
また、この時に夢を見ます。
レム睡眠中は心拍数や呼吸数が増えて不規則になるので、呼吸は浅くなります。
快眠のために「やるといいこと」「悪いこと」
寝落ちは気持ちいいかもしれませんが、寝落ちしてしまうのは慢性的な寝不足のサインになります。
脳にとっての睡眠は、目覚めている間に脳に溜まる睡眠物質を、眠っている間に分解し、目覚めた時に睡眠物質を貯めて、睡眠導入をしやすくするという繰り返し作業になります。
そのため1日だけ長く眠るということは、脳の仕組み上あまり合理的ではありません。
脳はその時々で睡眠を調整しているので、長期的なトータルの睡眠時間を重視する必要があります。
そのため、毎日15分早めに寝ることでトータルの睡眠時間を稼ぐようにしましょう。
二度寝をどうしてもしたいときは、平日と同じ起床時間に一度起きて、カーテンを開けて周りを明るくしてから二度寝することをオススメします。
ちなみに、どうしても眠れないということがあるような夜は、寝る時間は遅くとも、朝の一度起きる時間だけは平日と変えないように心がけましょう。
睡眠のまとめ
日中に光をしっかり浴びることによって、概日リズムが安定し、睡眠の質の向上と日常生活のメリハリをつけることができます。
睡眠の量だけでなく、質に目を向けることが大切です。
また、他人と睡眠を比べないことも大切になります。
ストレスによるバイタルサインの変化
脈拍
脈拍とは、体表面から触診できる動脈の拍動のこと
測り方
人差し指・中指・薬指をそろえ、反対の手首の外側にある動脈で15秒×4の心拍数を測定します。
正常値
60以上100以下の範囲が正常範囲内
※正常値は年齢によって異なる。
※また心拍数は、1分間に心臓がどれだけ心臓が拍動しているかどうか(心電図で示す値)であり、厳密に言えば異なる。
メンタルとの関わり
過度の緊張にさらされると、交感神経が優位になり脈拍が増加します。
1分間に100以上の拍出は心臓にとって負担が大きくなっている状態です。
心臓は自律神経によってその拍動をコントロールされているため、脈拍をセルフモニタリングすることにより、ストレスや緊張を自覚する目安の一つとして使うことができます。
血圧
血圧とは、血液を血管が押し出す力のこと
測り方
・血圧計を使用し、測定
・血圧は1日の中で変動がみられ、測定時の状態によっても数値が異なります。
→測る時間帯や状態は、一定に保つことが重要
①リラックスした状態
②排尿排便は済ませる
③座った姿勢で腕帯を正しく巻く
④毎日同じ時間に測る
⑤寒すぎたり暑すぎたりしない部屋で
⑥飲酒・カフェインなどをとらない
(例)[起床時] 起きて1時間以内(トイレを済ませ、服薬や食事の前に。)
[就寝前] 就寝1〜2分前
正常値
・年齢や性別、遺伝などによって個人差あり。左右差もある。
・概ね120/80±20程度が至適血圧の範疇。
メンタルとの関わり
血管壁の収縮は自律神経によって支配されています。
自律神経障害を呈することが多い精神障害では、正常な値に比べて変動や異常な数値が表れる例が少なくないと言われています。
また過度な労働や生活習慣の乱れによって、血圧が正常な値から逸脱している場合、血圧を把握することで生活を改める指標になります。
血圧は,自律神経にも関わりバイタルサインのなかでもより体質などによって
変動が表れますので日々の変動をチェックすることが大切です.
呼吸
呼吸は、1分間に行われた換気(吸って吐いたとき)の回数の値をさす。
測り方
1分間の呼吸数を評価する
※「数えられている」「数える」と意識すると大抵呼吸の回数がおかしくなるため、自分自身ではなく本人が気づかないうちに他人に測ってもらうことが望ましい。
※また呼吸数を本人が計測することは難しいため、「パルスオキシメーター」を用いて酸素飽和度を確認することをおすすめします。
正常値
正常とされている値は安静時16〜20回/1分程度
メンタルとの関わり
呼吸においては、吸う息は交感神経、吐く息は副交感神経を促進する働きがあります。
呼吸回数の増加は急激に状態が悪くなることの予兆(例:過呼吸、吐き気)でもあり、合併症の早期発見のための重要な身体所見と言われています。
規則正しい呼吸は自律神経の安定を指す指標のひとつであり、「苦しい呼吸だな」「いつもと違う呼吸の仕方だな」と変化があるときには、ストレスなどに対する自律神経の乱れや酸素不足等の判断にもなります。
そのため呼吸の回数を測ることで身体の変化に気づくことができます。
体温
発熱がある場合、なんらかの身体異常や不調を考察するバロメーターとなる。
測り方
体温計により測定する。
正常値
36.5(±0.5℃)とされるが、個人差あり。
平均体温に対してどの程度差があるかに対して注視する。
人間にはその体内にとっての基準となる体温が存在します。
この値を守ろうとする機構を「ホメオスタシス」といいますが、これが乱れている場合なんらかの身体異常が起こっている可能性がある。
メンタルとの関わり
本人が自覚できない健康状態は、時に体温など客観的データに思わぬ形で表出することがあります。
たとえばある環境などによってストレスがかかり、免疫が下がってしまった場合発熱する可能性もあります。
体温を測ることで身体状況をより詳細に確認することができます。
記載:おりたメンタルクリニック医師
■オンライン診療メンタルヘルス院について■
休職相談を扱う"オンライン診療専門"の
「オンライン診療メンタルヘルス院」もあります。
休職について悩まれている方は、お気軽にご相談ください。